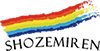「何を研究するか」
それはゼミの核と言ってもよい非常に重要な要素です。
経営や会計、マーケティングといった大まかな分類が一般的ですが、
一見同じ研究内容に見えるゼミでも、よく見てみると全く異なる研究を行っている場合があるので注意が必要です。
2年間同じ時間を過ごす先生との相性も重要な要素の一つです。
自由に研究をさせてくれる先生や、みっちり鍛えてくれる先生、
経験豊富な先生や、ゼミ生視点に近い若い先生など様々です。
自分の力がフルに発揮される環境とはどのようなものか、吟味する必要があります。
授業の形式もゼミごとに大きな違いがあります。
代表的なものとしては、担当者を決めての発表、輪読、ディスカッション、先生による講義などがあげられます。
また、そのゼミが目指すものによっても進め方は大きく変化します。
大会での入賞を目標とするゼミ、他大との研究発表に焦点を当てるゼミ、
日々自らの成長のために研究に勤しむゼミなど、到達点はそれぞれ別の場所にあります。
ゼミに所属する人、その人たちが作り出す雰囲気もゼミを選ぶ際に考慮すべきところです。
同じ興味関心を持ってともに活動する仲間は、2年間のゼミ生活に少なからず影響を与えます。
各ゼミには伝統や風習など様々な特色があります。先輩やOBなどと縦のつながりが強いゼミ、
授業外でも交流が盛んなゼミ、大学生活を捧げるほど研究に熱中するゼミなど、あげたらきりがありません。
重要でありながら、紙媒体だけではつかみづらい要素なので合同説明会や相談会など、生の声を通して情報収集してください。
どれほどの時間を注ぎ込むか、もちろん個人のやる気次第ですが、所属するゼミの方針に大きく左右される部分でもあります。
大別すると、大学生活の中心にゼミを置き、青春を研究に捧げる、いわゆる「ガチゼミ」、
他の活動と両立しながら研究に励むゼミ、その中間のゼミに分類されます。
テーマ
先生
形式
雰囲気

文化
活動頻度